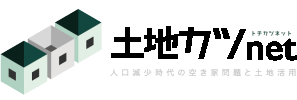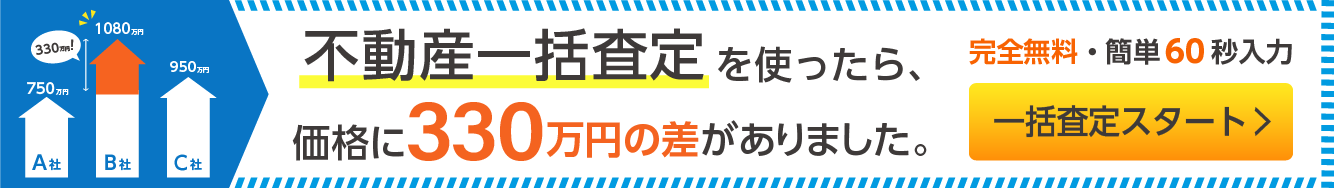不動産投資などでマンション・アパートの購入を考えている、居住目的で家を探している、土地活用の方法を探している方で、第一種中高層住居専用地域を検討している方は、
第一種中高層住居専用地域とは何だろう?やどんな建物が建てられるのだろう?と疑問に思っているのではないでしょうか。
この記事では、そんな疑問にお答えするべく、
- 第一種中高層住居専用地域の特徴
- どんな建物が建設可能なのか
- 第一種中高層住居専用地域で考えられる土地活用
をご紹介します。

そもそも、自分が住んでいる地域、もしくはこれから購入しようとしている地域が第一種中高層住居専用地域なのかどうか調べたい方には下記の記事がおすすめです。
用途地域の調べ方をご紹介しています。
自分の土地の上に何を建てるのかは、原則として所有者の自由であるはずです。しかしながら、現実には用途地域と呼ばれる規制によって、建てられる建物は制限され、違反すると罰則もあります。では、なぜ自分の土地なのに、建物を自由に建てること[…]
第一種中高層住居専用地域とは
第一種中高層住居専用地域とは、第一種中高層住居専用地域は、その名の通り「中高層」の住宅が見られる地域です。
具体的には、低層住居専用地域の絶対高さ制限がなく、容積率は最大500%まで認められているため、4階建て以上のマンションを建てることが可能になります。
また、店舗に対する制限が、業種・面積ともに緩和されており、小規模な食品スーパーやファミリーレストランなどの飲食店も営業できます。
これは、低層住居専用地域にはない大きなアドバンテージでしょう。
店舗の出店状況しだいですが、日常生活なら近くで済んでしまう第一種中高層住居専用地域は、利便性が良く戸建てやマンションがあることで、それなりに人口密度の高い地域です。
もちろん、低層住宅も多いので、高さの異なる建物が入り混じっています。
その反面、あくまでも住居専用地域ですから、人が集まりやすい大型店舗や遊戯施設は立地できず、静けさも持ち合わせている良環境を形成しています。
他の用途地域と比較してみよう
第一種中高層住宅専用地域の特徴をわかりやすくするために、他の用途地域と比較してみましょう。
| 用途地域の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 高さ制限(10mまたは12m)から3階以下の低層住宅に限定され、住環境の保護が最優先される地域。店舗や事務所は、小規模な兼用住宅で特定条件を満たさなければ建てられません。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域と異なるのは、小規模な店舗が建築を許されることで、日常生活に深く関連する店舗だけが、2階以下を条件として営業可能です。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 高さ制限がなくなり、他の規制で高さが制限されなければ、4階建て以上のマンションを建てられる地域。 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 店舗の要件が緩和され、多業種化・大規模化されますが階数は2階以下の地域。 |
| 第一種住居地域 | 住居「専用」ではない地域で、店舗や事務所の階数制限がなくなります。 |
| 第二種住居地域 | 大規模な店舗まで建築可能になり、事務所の床面積要件がなくなります。 |
| 準住居地域 | 第二種住居地域の条件に加え、劇場や映画館が建てられ、自動車修理工場の床面積要件が緩和されます。 |
| 田園住居地域 | 低層住宅と農地の混在により、良好な住環境を保つ地域。 |
| 近隣商業地域 | 商業系の用途地域で、店舗の床面積要件がなくなります。俗施設の一部が限定されるだけで、商業施設の制限はありません。 |
| 商業地域 | 工場以外の制限はなく、商業施設の集積で中心市街地を形成している地域。 |
| 準工業地域 | 商業地域と同様にほぼすべての建物が建てられる地域で、危険性の大きい工場や大量の危険物を扱う施設だけが制限を受けます。 |
| 工業地域 | 工場の制限がなくなる一方、病院が建てられず、店舗の床面積要件が加わります。 |
| 工業専用地域 | 専用住宅・兼用住宅に関係なく、工業専用地域は住宅の建築が禁じられている地域。 |
第一種中高層住居専用地域に建てられる建物・建てられない建物
次に第一種中高層住居専用地域に建てられる建物と建てられない建物をみていきましょう。
第一種中高層住居専用地域に建てられる建物
第一種中高層住居専用地域で建てられる建物は以下の通りです。
| 建物の用途 | その他の制限 |
|---|---|
| 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | |
| 兼用住宅(非住宅部分1/2未満かつ50㎡以下) | 非住宅部分の用途制限あり |
| 店舗等で500㎡以下(2階以下) | 飲食店、物品販売店舗等 |
| 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | |
| 大学、高等専門学校、専修学校等 | |
| 図書館等 | |
| 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | |
| 神社、寺院、教会等 | |
| 病院 | |
| 公衆浴場、診療所、保育所等 | |
| 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | |
| 老人福祉センター、児童厚生施設等 | |
| 単独車庫 | 300㎡以下、2階以下 |
| 建築物附属車庫 | 3,000㎡以下、2階以下 |
| 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等(作業場の床面積50㎡以下) | 原動機0.75kW以下、2階以下 |
| パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場の床面積50㎡以下) | 自家販売、原動機0.75kW以下、2階以下 |
この区域には、マンションや戸建てなどの住居以外にスーパーやコンビニなどの出店が可能です。コインランドリーも政令の定めるもので500㎡以下なら出店が可能です。
また、住宅兼用で50㎡以下なら、学習塾や華道教室なども経営が可能なので、お子さんから高齢の方まで、近くに習い事の教室がある環境になります。
第二種中高層住居専用地域と比べると第一種中高層住居専用地域には大型の商業施設はありませんが、その分落ち着いた雰囲気と利便性を兼ね備えた用途地域になります。
幼稚園なども建設可能ですし、小さいお子さんのいる若い家族から遠くまで買い物へ行く高齢の夫婦も住みやすく、戸建てを購入するには良い区域ではないでしょうか。
第一種中高層住居専用地域に建てられない建物
第一種中高層住居専用地域で建てられない建物は以下のようになります。
- 3階以上または500㎡超の店舗等
- 事務所等(兼用住宅を除く)
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、風俗施設
- 自動車教習所
- 3階以上または300㎡超の単独車庫
- 3階以上または3,000㎡超の建築物附属車庫
- 倉庫
- その他、建てられる建物に記載以外の工場
第一種中高層住居専用地域で受ける制限
- 建ぺい率
- 容積率
- 斜線制限
- 日影規制
の観点からみていきたいと思います。
建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことで、
で求められます。
第一種中高層住居専用地域の建ぺい率は、30%、40%、50%、60%のうち都市計画で定める値と定められています。
例えば、300平米の土地を持っているとして、その土地の建ぺい率が50%の場合は、建物が建てられる上限の面積は150平米になります。
第一種中高層住居専用地域にマンションやアパートを建てる際は、建ぺい率が何%なのかを市区町村の都市計画課に問い合わせ、自分が希望する建物が建てられるかどうか検討するようにしましょう。
容積率
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことで、
で求められます。
ちなみに、延べ床面積とは、その建物の床面積の合計のことです。2階建ての建物の場合、1階と2階の床面積の合計になります。
ただし、延べ床面積に含まれない部分として、「玄関」「バルコニー・ベランダ」「ロフト」があげられ、面積を割引いて換算する緩和措置を設けている部分としては「地下室」「ビルトインガレージ」などが挙げられます。
第一種中高層住居専用地域の容積率は、100%、150%、200%、300%、400%、500%のうち都市計画で定める値です。
例えば、敷地面積が300平米、容積率が200%の場合、延べ床面積は600平米になります。
第一種中高層住居専用地域には高さ制限はありませんが、容積率によって、延べ床面積に制限がかけられるため、制限なく高い建物を建てられる訳ではありません。
斜線制限
斜線制限とは、道路境界線または隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限することにより、道路上空や隣棟間に一定の角度をもって空間を確保しようとするものです。
第一種中高層住居専用地域の斜線制限は、
適用距離:前面道路の反対側の境界から20m、25m、30m、35m(容積率による)
高さ制限:前面道路の反対側の境界からの距離×1.25 (特定行政庁指定区域は1.5)
隣地境界からの距離×1.25+20m(特定行政庁指定区域は2.5+31m)
北側隣地境界(道路の場合は反対側の境界)からの距離×1.25+10m
※日影規制の対象区域は除外
となっています。
日影規制
日影規制とは、隣地にできる日陰の時間制限のことです。
冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、全く日が当たらないことのないように建物の高さを制限する規制です。
周囲の日照を確保して、快適な暮らしの妨害を防ぐ目的で決められています。
第一種中高層住居専用地域での日影規制は、
測定面の高さ:4mまたは6.5mを自治体が条例で指定
時間制限:以下の1~3を自治体が条例で指定
- 隣地境界から10m以内は3時間、10m以上は2時間
- 隣地境界から10m以内は4時間、10m以上は2.5時間
- 隣地境界から10m以内は5時間、10m以上は3時間
のように定められています。
第一種中高層住居専用地域以外で中高層のマンションが建ちやすいエリア
第一種中高層住居専用地域は「中高層」の住宅が見られる地域ということもあり、第一種中高層住居専用地域以外にどの地域が中高層のマンションを建てられるのか気になった人もいたのではないでしょうか。
中高層のマンションが立ちやすいエリアは、他にも
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 第二種中高層住居専用地域
があります。
それぞれの住宅地域と第一種中高層住居専用地域との違いを簡単に説明すると、
第一種・第二種住居地域と第一種中高層住居専用地域との違いは、マンションや一戸建てのそばでも店舗や飲食店、事務所、ホテルなどを建てても良い点です。
また、第二種住居地域は、第一種住居地域と比べ、さらに建てられる店舗のバリエーションが広くなり、パチンコ屋・カラオケ店・勝馬投票券発売所等の遊戯施設を建てることができます。
そのため、第一種・第二種住居地域の方が第一種中高層住居専用地域に比べ、周りにお店が多くより便利でしょう。
第二種中高層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域の違いは、延べ床面積が1500㎡までの物品販売を含む店舗・飲食店・オフィスビル・ガソリンスタンドが建てられるという点です。
そのため、第二種中高層住居専用地域は、第一種中高層住居専用地域と比べてより高く広い店舗・飲食店が建てられます。
 | 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング |
|---|---|---|
| 運営開始時期 | 2001年11月 | |
| 対象エリア | 全国 | |
| 累計利用者数 | 700万人 | |
| 提携会社数 | 1,300社 | |
| 同時依頼社数 | 6社 |
第一種中高層住居専用地域での土地活用の考え方
第一種中高層住居専用地域では、4階建て程度のマンションが建てられること、営業できる店舗の種類が増えるので、活用の幅が広がり悩むかもしれません。
まずは、住宅・店舗にするか、それとも土地で活用するか決めてはどうでしょうか。
戸建てを建てて賃貸にするという方法もありますし、マンションについては、大学・高専・専修学校(専門学校)が建てられる地域なので、もし近くにあれば単身用のワンルームマンション、なくても家族向けマンションのニーズが高いことは予想できます。
もし、マンションを建てる資金に不安がある場合、等価交換方式でマンションの一部を手に入れれば、部屋を賃貸することで賃貸経営を始められます。
また、店舗面積が500㎡まで許されることや、基本的に住宅地なので、周辺住民をターゲットにした販売業・サービス業も需要は高いと思われます。
低層住居専用地域と同じく、倉庫が建てられずコンテナ倉庫は置けません。
その他、駐車場は賃貸経営に比べて収益性は低いですが、他に転用しやすいメリットがあり、2階までの機械式駐車場やコインパーキングも可能です。
事業の選択ももちろんですが、自身で行うのなら運用を開始した後の手腕も問われます。経営は難しい、あまりリスクを取りたくないといった場合は、コンビニやコインランドリーなどのチェーン店に土地を貸すという方法もあるでしょう。
不動産会社やコンサルタントなどに相談して、最適な土地活用を探りましょう。
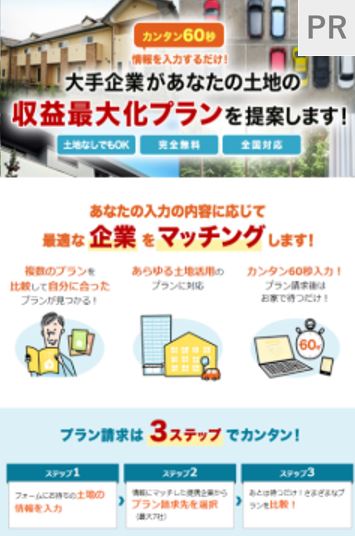 | 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング |
|---|---|---|
| 運営開始時期 | 2001年11月 | |
| 対象エリア | 全国 | |
| 累計利用者数 | 700万人 | |
| 提携会社数 | 50社 |