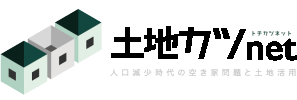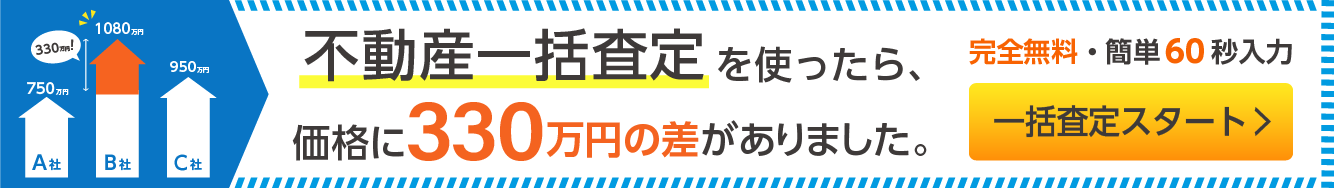現在日本の土地には立てて良い建物が厳しく規制されている地域(用途地域)があります。
第二種低層住居専用地域も用途地域の1つです。
第二種低層住居専用地域にはどのような建築制限があるのか、また第一種低層住居専用地域との違いは何か。
この記事を読めば、第二種低層住居専用地域とは何か、どのような制限やメリット・デメリットがあるのかがわかります。

1 用途地域とは何か
1.1 都市を整えるための制度
工業エリアと住宅エリアが混在してしまったりすると、生活環境が悪くなってしまったり業務の利便性が失われてしまいます。
そこで、エリアを分けて都市を整備することで、住環境を守り住みやすく便利にする制度が作られました。
これが、用途地域です。
用途地域は日本全国すべての土地の用途を指定しているわけではありません。
主に人が多く密集して住んでいるエリアに当てられることが多く、乱開発が行われないように調整されているのです。
用途地域は全部で13種類に分けられていて、大きく分類すると住居系・商業系・工業系の3つになります。
用途地域が定められている土地では住宅や店舗など建物の使い方が決められています。
さらに、高さや容積率なども定められており、区域内の秩序を乱さないようにルールが作られています。
1.2 用途地域の種類
用途地域には第二種低層住居専用地域の他にどのような区域があるのでしょうか。
区域によっては、住宅の建設を不可とするような場所もあります。
| 目的 | 区域 | 概要 |
|---|---|---|
| 住居環境を最優先 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域。小規模な店舗やオフィスを兼ねる住宅などが他建築できる。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域。150㎡までの一定お店が建築可能。コンビニなども出店できる。 | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域。大学などが設置できるが、住宅専用地域のためオフィスビルなどは建築できない。 | |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層の住宅のための地域。2階以下で1500㎡までのお店や事務所、大学などを建築できる。 | |
| 住居環境の保護 | 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するための地域。大規模なマンションなどが建築できる。パチンコ店やカラオケボックスなどの建築は禁止。 |
| 第二種住居地域 | 主に住環境を保護する地域。大規模店舗、カラオケボックスなども建築できる。 | |
| 道路沿いで自動車関連施設と住居の調和 | 準住居地域 | 住宅系の用途地域で最も許容範囲が広い地域。200㎡より小さければ、映画館や営業用倉庫なども認められている。 |
| 農地と住居の調和 | 田園住居地域 | 低層住宅と農地の混在で良好な住環境を保つ。平成30年4月から導入予定の新しい区域。 |
| 映画館や倉庫、車庫が立てられる | 近隣商業地域 | 近隣の住宅の住民に日用品などの販売を主とする商業地域。飲食店、展示場など建設可能。 |
| 商業地域 | 商業の利便性を進めるための地域。一定の工場などを除いてほとんどの用途の建築物をたてられる。 | |
| 準工業地域 | 住宅と工場が混ざる地域。火災の危険や健康への有害度が高い工場は建設禁止。 | |
| 工業地域 | 環境悪化の恐れがある工場も建築可能なエリア。住宅・店舗の建設は可能だが、学校や病院は不可。 | |
| 住居は建てられず、工場のみ | 工業専用地域 | 石油類やガスなど危険物の貯蔵・処理の量が多くても可能。住宅や店舗は建築不可。 |
1.3 地価が高くなる用途地域とは
最も需要が高いのは、制限が少なく家でもお店でも建設することができる商業地です。
逆に用途への制限が厳しい第二種低層住居専用地域は一般的に土地価格が安くなります。
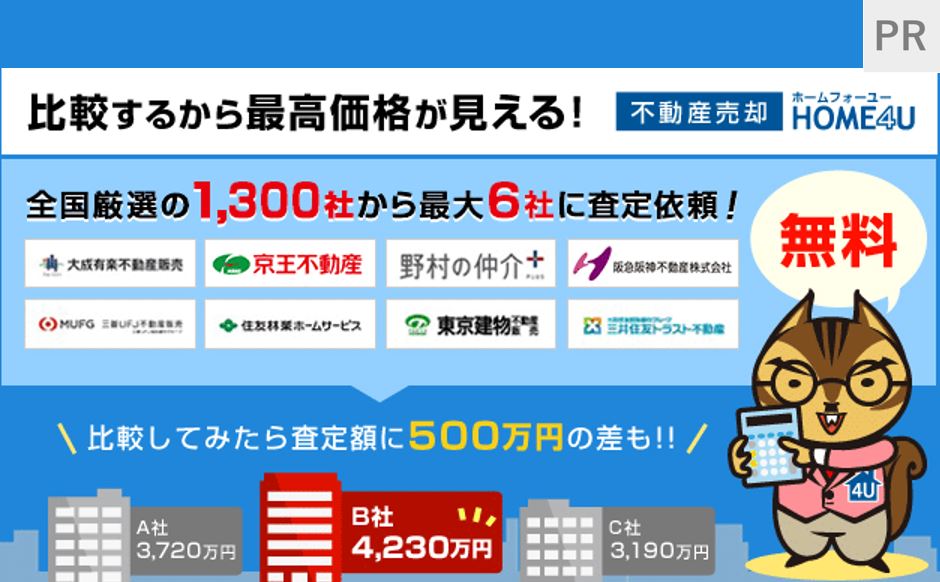
1.4 用途地域の調べ方
売却や購入する不動産は契約前に用途地域を調べておいた方が良いでしょう。
売却の場合はどんな人に販売できるのか、土地活用はできるのか考えるための参考になるからです。
購入する際は、事前にどれくらいの高さの家が建てられるのか知ることができますし、周辺に今後どんな建物が建つのかある程度推測できます。
お子さんなどがいる人は特に環境が気になるのではないでしょうか。
最も簡単な調べ方は不動産屋さんに「ここの用途地域を教えてください」と聞くことです。
それが難しいという方は不動産が所在する市役所に連絡し、「用途区域を教えてください」と連絡を入れましょう。
仕事が忙しい方の場合は、Web上で調べる方法もあります。
「市町村 都市計画図」で検索すると、各地域の区域がわかります。
詳しい使い方はこちらの記事で千葉県柏市を例に解説しています。
自分の土地の上に何を建てるのかは、原則として所有者の自由であるはずです。しかしながら、現実には用途地域と呼ばれる規制によって、建てられる建物は制限され、違反すると罰則もあります。では、なぜ自分の土地なのに、建物を自由に建てること[…]
その他の方法として、家を購入されている方は契約前に不動産会社からもらった「重要事項説明書」の用途地域の枠を確認するというやり方もあります。
2 第二種低層住居専用地域とは何か。第一種低層住居専用地域との違いは?
第二種低層住居専用地域とは、低層住宅の良好な住環境を最優先に保護する地域です。
第一種低層住居専用地域との違いは、2階以下で延床面積(床面積の合計)が150㎡以内の小規模な飲食店や店舗を建設できる点にあります。
第一種低層住居専用地域の場合は、居住用住宅と店舗の兼用建物のみ建設可能です。
店舗は業種を問わず、高さ2階以下という制限を受けるため、景観において第一種低層住居専用地域とほとんど変わりません。
大きな違いとしては、日用品販売店(コンビニ)が出店できることでしょうか。
3 第二種低層住居専用地域の用途制限
低層住居の良好な住環境を守るため、第二種低層住居専用地域の用途制限は厳しく設定されています。
30%、40%、50%、60%のうち都市計画で定める値
50%、60%、80%、100%、150%、200%のうち都市計画で定める値
適用距離:前面道路の反対側の境界から20m
高さ制限:前面道路の反対側の境界からの距離×1.25
北側隣地境界(道路の場合は反対側の境界)からの距離×1.25+5m
10mまたは12mのうち都市計画で定める値
適用対象:軒高7m以上または3階以上
測定面の高さ:1.5m
時間制限:以下の1~3を自治体が条例で指定
1.隣地境界から10m以内は3時間、10m以上は2時間
2.隣地境界から10m以内は4時間、10m以上は2.5時間
3.隣地境界から10m以内は5時間、10m以上は3時間
都市計画で定める場合は1.5mまたは1m
4 第二種低層住居専用地域で建てられる建物・建てられない建物
| 建物の用途 | その他の制限 |
|---|---|
| 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | |
| 兼用住宅(非住宅部分1/2未満かつ50㎡以下) | 非住宅部分の用途制限あり |
| 店舗等で150㎡以下(2階以下) | 日用品販売、食堂、理髪店等 |
| 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | |
| 図書館等 | |
| 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | |
| 神社、寺院、教会等 | |
| 公衆浴場、診療所、保育所等 | |
| 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | |
| 老人福祉センター、児童厚生施設等 | 600㎡以下 |
| 建築物附属車庫 | 建築物面積の1/2以下、600㎡以下、1階以下 |
| 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等(作業場の床面積50㎡以下) | 原動機0.75kW以下、2階以下 |
| パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場の床面積50㎡以下) | 自家販売、原動機0.75kW以下、2階以下 |
【建てられない建物】
- 3階以上または150㎡超の店舗等
- 事務所等(兼用住宅を除く)
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、風俗施設
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 病院
- 自動車教習所
- 建築物附属車庫以外の車庫、倉庫
- その他、建てられる建物に記載以外の工場
5 第二種低層住居専用地域に住むメリット・デメリット
第二種低層住居専用地域に住むメリットには以下のようなものがあります。
第二種低層住居専用地域に住むメリット
- コンビニや小さな商店街など生活に必要最低限なお店が周りにあり便利
- 高さの低い建物が多いため、比較的日当たりがよい
- 閑静で住みやすい
一方デメリットとしては、
第二種低層住居専用地域に住むデメリット
- 周りに大きなスーパーマーケットがない
- 小規模なお店を建てられるため、第一種低層住居専用地域と比較して閑静でない
があげられます。
大きなスーパーマーケットなどのお店は建てられませんが、コンビニや小さなお店が側にあれば、生活をするには十分なのではないでしょうか。
第二種低層住居専用地域は、小さなお店がそばにあり、住みやすいという良いところどりの住むのに適した地域だといえます。
6 第二種低層住居専用地域での土地活用の考え方
住宅が多い第二種低層住居専用地域での土地活用は、第一種低層住居専用地域と同様に、戸建て・アパートの賃貸住宅がメインとなります。
それでも、150㎡以下の独立店舗が営業できる点は、ずいぶんと活用の幅を広げます。
もし、床面積150㎡(約45坪)のイメージができなければ、平均的な(郊外店舗よりも狭く中心街店舗よりも広い)コンビニを思い浮かべてください。
作業場の床面積に制限はあっても、多くの店舗が出店できるとわかるはずです。
また、一般に住宅よりも店舗のほうが構造は単純で、賃料を高く設定できます。
しかも、改装費用は賃貸人の負担にできますし、スケルトンでの原状回復契約が可能、居抜き物件として次の賃貸人への引き継ぎも可能など流動性に優れています。
つまり、所有者は店舗としての「箱」を用意すれば良く、第二種低層住居専用地域での最大のメリットである貸店舗経営は優先的に考えていきたいところです。
ただ、周りはほとんど低層住宅ですから、騒音・臭いトラブルには気を付けましょう。
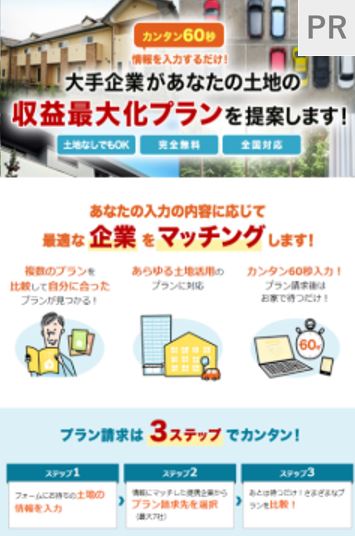 | 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング |
|---|---|---|
| 運営開始時期 | 2001年11月 | |
| 対象エリア | 全国 | |
| 累計利用者数 | 700万人 | |
| 提携会社数 | 50社 |